-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
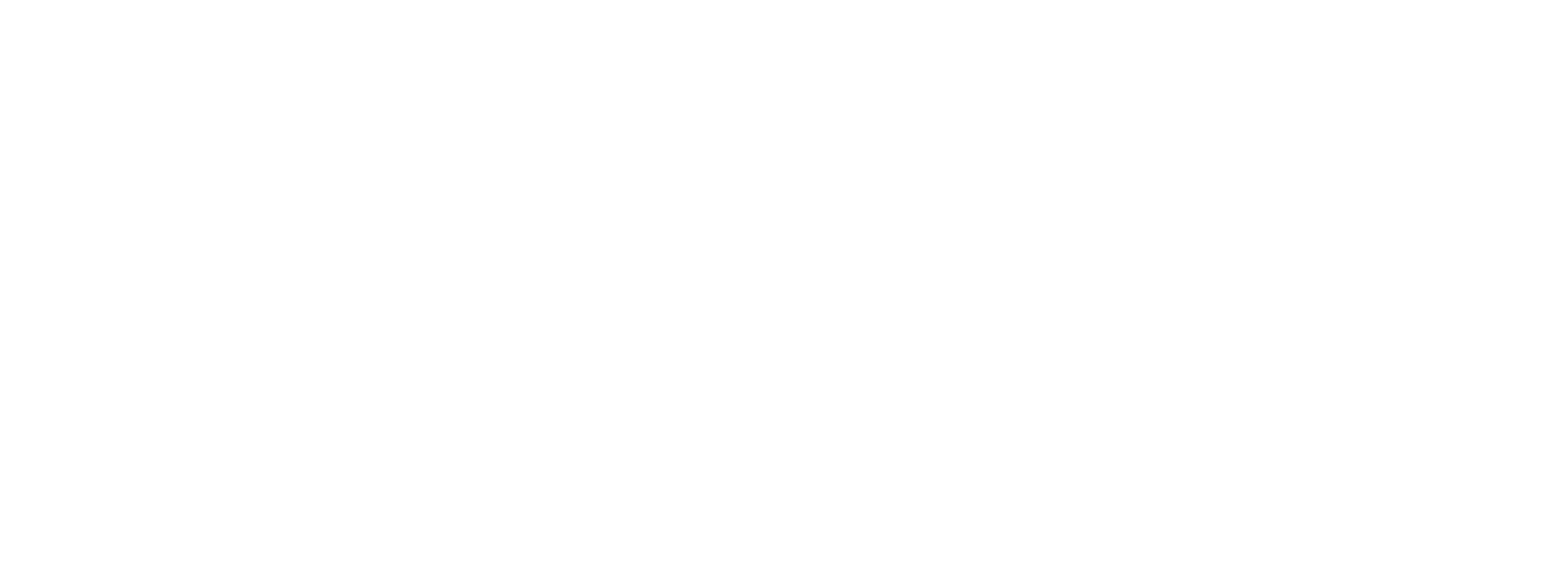
皆さんこんにちは!
株式会社小倉工務店、更新担当の中西です。
さて今回は、
~設計~
ということで、造作工事における設計の目的・設計手法・注意点・設計者と施工者の連携ポイントまで、現場と図面の両面から深掘りしてご紹介♪
建築工事における「造作」とは、完成した構造体に対して内装を仕上げるための木工・建具・家具などの工事を指します。そして、その造作部分を設計段階でどう描くかは、空間全体の印象や使い勝手、美しさを大きく左右する非常に重要な要素です。
造作工事における設計とは、空間の使用性や美観を形づくる“細部設計”のことです。
構造体や間取りといった「大きな設計」に対し、造作設計は「暮らしや使い方を形にする設計」です。
建具枠(ドア・障子・引戸など)の詳細設計
カウンター、棚、造作収納の寸法・素材・固定方法
笠木、廻り縁、巾木、見切り材などの意匠部材
階段手すり、ニッチ、テレビ台、ベンチなどの機能造作
空間に合わせた“オーダーメイド家具”や“壁面一体型収納”など
🧱 単なる内装部材ではなく、「建築の一部としてデザインされた機能物」であるのが造作設計の特徴です。
使用者の体格、動作範囲、隣接家具との関係を考慮
例)キッチンのカウンター高さ → 使用者の肘下高さ −10cm
奥行・高さ・棚の間隔など、使いやすさ=寸法の正確さ
📐 建築寸法の「910モジュール」だけでなく、人体寸法(アーゴノミクス)との両立が必要です。
無垢材/突板/メラミン/ポリ合板/スチール/アクリル等
耐水性、耐熱性、傷つきにくさ、メンテナンス性も考慮
住宅では温もり、商業施設では清掃性・意匠性が求められる
🎨 材料の選定ひとつで、空間の印象がガラッと変わる=デザインの要です。
床と壁、壁と天井、木部とクロス、造作と建具の取り合いを図面で明確に
クリアランス(隙間)や伸縮の逃げを考慮する
コーナー部分・端部の納め方(見切り材 or 面取り)で仕上がりが変わる
🧩 デザインの美しさは「納まりの美しさ」で決まります。施工者との連携が特に重要です。
加工のしやすさ、材料の搬入経路、重さ・強度を踏まえて設計
天井・壁の傾きや誤差を見越した調整幅(逃げ寸法)を盛り込む
図面上の寸法が現場で実現可能かを確認
🛠️ 「デザイン先行すぎて施工できない」は、設計ミスではなく設計責任です。
可動棚や扉の交換部品が後から手に入る設計に
壁内に隠れる金具は点検口・メンテナンスルートの確保が必要
水まわりや荷重のかかる箇所は耐久性・防水性を考慮
🔧 一時の美しさよりも、「10年後の使いやすさ」が設計の真価を問われます。
例:引き戸の建具枠と造作収納が干渉
縦枠の厚みや建具の開閉範囲を図面上で見落としがち
カウンター裏に配線スペースなし
埋め込み照明と木下地の位置が干渉
無垢材での造作→湿気で反り、扉が閉まらない
合板でもジョイント部のクリアランス不足
📌「図面では完璧」でも、現実の“木のクセ”や現場環境まで想定する設計力が問われます。
造作設計は、図面だけで完結しません。現場と連携して初めて形になります。
着工前に現場採寸・実測による設計再調整
図面に反映されない加工方法・固定方法の相談
現場からのフィードバックを設計に還元するPDCA
👷♂️ 現場の職人と「納まりの言語」を共有できる設計者こそ、信頼されます。
構造体ができあがり、設備も整い、最後に空間を形作るのが造作工事です。
その設計において大切なのは
✅ 人の動きと寸法への配慮
✅ 材料の特性と美観のバランス
✅ 現場で施工できる現実的な納まり
✅ 仕上げのための下地としての正確さ
✅ 長く使えるための耐久設計
「図面1枚に空間の使いやすさと美しさを込める」
それが、造作設計者の使命であり、職人との信頼関係を築く第一歩でもあります。
株式会社小倉工務店では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社小倉工務店、更新担当の中西です。
さて今回は、
~確認事項~
ということで、今回は、造作工事における失敗を防ぐための事前確認事項を現場目線で深掘りし、プロの視点からチェックすべきポイントを網羅的に解説していきます!
造作工事とは、建築のなかでも「空間の仕上がりを左右する繊細な工事」です。
わずか1mmのずれが目立ってしまったり、材料の納まりが悪ければ、全体の美観や機能性に大きな影響を及ぼします。
だからこそ大切なのが、着工前の“事前確認”の徹底です。
造作工事とは、建築物の構造体ができた後に行われる内装・仕上げ・空間形成のための木工事や取り付け工事全般を指します。
天井・壁・床の木下地組み(大工工事)
建具枠・巾木・廻縁などの取り付け
カウンター・棚・収納などの現場家具製作
間仕切りや化粧パネルの取り付け
石膏ボード貼りと開口部納まりの調整
造作は、仕上げ材の「下地」としての精度が最も問われる工程であり、仕上げ工事との“橋渡し役”でもあります。
平面図、断面図、展開図、詳細図をすべて確認
設計変更やVE(バリューエンジニアリング)対応が反映されているか
建具、収納、造作家具など細部の寸法・高さ・納まりが整合しているか
「図面通りに造ったけど収まらない」は事前確認の甘さが原因です。
電気・設備・左官・クロス・塗装との干渉箇所を事前にチェック
コンセント・スイッチ・給排水位置の通り・高さ確認
先行配管・配線が造作に支障をきたさないか?
️ 職人同士の連携が甘いと、現場でやり直し=コスト増につながります。
棚板・天板・框材・仕上げパネルなどの注文品・加工品の寸法・色・仕様確認
納品日が造作工期に間に合うか?現場搬入ルートの確保はできているか?
支給材の品番ミス・数量不足・左右逆対応なども事前に要確認
材料がなければ現場は止まります。「納期と数量」は最重要です。
天井高さ・床高さ・芯墨・GL(グランドライン)の確認
壁・建具・間仕切りの芯と下地組みの基準が一致しているか
レーザー墨出し器を用いて水平・垂直精度を確保
墨が正しくなければ、すべてがズレる=致命的な施工不良に直結します。
石膏ボードの目地位置やサイズ、ビスピッチの確認
壁掛けテレビ・手摺・棚などの荷重がかかる箇所には合板下地が必要
コンパネか石膏ボードか、壁厚・断熱材の有無も含めて調整
「仕上げ後に下地が足りなかった」では手直しが困難なケースも多々あります。
壁や天井の傾き、床の不陸、既存構造材とのクリアランス
既存壁・建具に新しい造作材がぶつからないか?
違う素材・年代の取り合いをどう納めるか事前に検討
“既存建物との対話”がリフォーム造作では特に重要になります。
クロス・塗装・タイルなどの仕上げ厚を想定した見切り調整
マスキングや養生方法、仕上げ材の収まりしろ(逃げ)の確認
塗装や左官前提の部材は下地処理までが造作範囲か?
「仕上げ職人が困らない造作」こそが理想の下地です。
現場内での作業スペース・材料置き場・電源の有無
作業台・スライド丸ノコ・釘打ち機・集塵機の持ち込み可否
騒音時間制限(マンションやテナント)などの現場ルール
段取りが悪いと「作業開始が遅れる=工期遅延」の原因になります。
カウンター高さ、手摺位置、棚の段数、コンセント位置など
現場での実寸確認やモックアップ提示が効果的
施工中に施主から変更指示が出た場合の対応ルールを明確化
「言った・言わない」がクレームの火種になるため、事前記録が大切です。
作業中の粉塵・切粉の飛散防止(集塵・養生)
床や壁の傷防止のためのブルーシート・養生ボードの事前設置
工事完了後の清掃・検査基準の確認
美しい仕上がりは、「きれいな現場」から生まれます。
造作工事は、建築の最後を彩る「仕上げの職人技」です。
しかし、そこに至るまでには、
✅ 図面の整合性確認
✅ 材料の準備と納期管理
✅ 他業種との取り合い調整
✅ 仕上がりイメージの共有
こうした“段取り”と“事前確認”がすべての基礎になります。
たとえ1mmのずれも許されない世界だからこそ、「造作工事は準備が9割」と言えるのです。
株式会社小倉工務店では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()